介護のために仕事を辞めるかどうか、悩んだことがある人も多いのではないでしょうか。
私もその一人でした。
離職を考えたとき、いちばんの不安はやはり「お金」でした。
自分の生活費に加え、親の介護費用もかかる。
収入がない中で、本当に生活していけるのか?
この記事では、私の実体験をもとに「介護離職後にかかる生活費」や「使える支援制度」について、リアルな数字で解説します。
介護離職で必要になる生活費とは?
介護が始まると、これまでの生活とは少し違う支出が発生します。
まずは、自分ひとりで暮らす場合に必要な生活費と、親の介護にかかる費用をそれぞれ見ていきます。
自分ひとりで暮らすための生活費(実例)
私自身がひとり暮らしをしている中で、実際にかかっていた月々の支出は以下の通りです。
| 項目 | 月額(円) |
|---|---|
| 家賃 | 70,000 |
| 食費 | 25,000 |
| 水道・光熱費 | 10,000 |
| 交通費 | 10,000 |
| 交際費 | 10,000 |
| 娯楽費 | 15,000 |
| 通信費 | 5,000 |
| 雑費 | 5,000 |
| 奨学金 | 15,000 |
| 合計 | 165,000円 |
親の介護でかかる費用(実例)
私の母は要介護1で、当時は以下のようなサービスを利用していました。
- デイサービス:1回あたり 約3,000円(1割負担)
※食事・入浴込み、7〜8時間の利用 - 週3〜4日利用 → 月額 約40,000円
また、親が同居することで以下のような生活費も上乗せされました。
- 食費の増加:月1万円程度
- 水道・光熱費の増加:月5,000円程度
- 医療費(通院や薬代):月5,000円程度
つまり、親の介護・生活にかかる費用は合計で月6万円前後多くなりました。
収入がない状態で自分の生活費+介護費用をまかなうとなると、かなり厳しいことがわかります。
介護で仕事を辞めるとき、収入ゼロでは生活できない?
「介護のために会社を辞めるしかない」と思っても、生活が成り立たなければ意味がありません。
実際には、収入が減る・なくなる前提で生活設計や制度の活用を考えることが大切です。
離職後に頼れる支援制度
1. 介護休業給付金(離職前)
最大93日間、給与の67%相当が支給されます。
勤務先で介護休業を取得できるなら、まずはこの制度の利用を検討しましょう。
2. 失業手当(離職後)
介護のためにやむを得ず離職した場合でも、条件を満たせば雇用保険の失業給付を受け取れます。
3. 高額介護サービス費制度
介護保険の自己負担額が一定額を超えた場合に、超過分が払い戻される制度です。
収入によって上限が異なります。
4. 医療費控除・障害者控除
医療費や介護費用が一定額を超えた場合、確定申告で税金の還付が受けられる可能性があります。
5. 自治体独自の支援
住んでいる地域によっては、在宅介護者向けの給付や助成金がある場合もあります。
市区町村の窓口や地域包括支援センターで確認しましょう。
私が離職せずに済んだ理由
私の場合、離職はせず、仕事を続けながら介護を続けました。
それが可能だったのは、いくつかの備えがあったからです。
- 生活費を数字で把握していたこと
→ どこまで収入が減っても生活できるかが見えていた - 資産形成を早めに始めていたこと
→ 万が一収入が途絶えても、一定期間は耐えられる余力があった - 制度を調べておいたこと
→ 自治体の支援や介護保険サービスをうまく活用できた - 在宅ワークが利用できたこと
→ 職場に相談して、完全リモートで仕事ができた
もちろん大変なことも多かったですが、「準備しておくことの大切さ」を改めて感じました。
まとめ|感情ではなく数字で「離職後の生活費」を考えよう
介護が始まると、気持ちの面でも追い詰められることが多く、「仕事を辞めてでも…」と考えてしまいがちです。
でも、離職は生活の基盤を失う大きな決断。
感情だけで動く前に、まずは生活費を数字で見える化することをおすすめします。
そのうえで、制度や支援をうまく使いながら、自分や家族にとってベストな選択ができるように、準備を進めていきましょう。

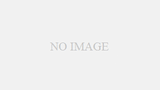
コメント