介護が始まったとき、職場や行政に相談することは重要です。しかし、実際には多くの人が相談できずに悩みを抱えています。今回は、介護に関する相談状況についてのデータ(三菱UFJリサーチ&コンサルティング「介護離職者の離職理由の詳細等の調査」)をもとに、私自身の体験も交えてご紹介します。
職場に相談しない人が6割以上
調査によると、介護について勤務先に相談したことがない人は61.7%にのぼります。
職場に相談しない理由としては、相談しづらい雰囲気や、キャリアへの影響を懸念する声が多く挙げられています。
6割以上が勤務先に相談をしてないという衝撃の結果です。職場の理解を得ずに在宅勤務を続けるのは、私の経験からはかなり難しいと思います。(私自身は不可能だったと思います)
行政の相談窓口の認知度が低い
市区町村の窓口について、「この相談先は知らない」と回答した人は35.3%、地域包括支援センターについては39.5%が「この相談先は知らない」と答えています。
行政の相談窓口の認知度が低いことが、介護者の孤立を招いている可能性があります。
認知症など介護が必要になったら、要介護認定を受けるためにも役所に行きましょう。
ケアマネジャーが最も頼りになる存在
介護に関する相談先として、最も「役に立った・助けになった」と感じたのはケアマネジャー(50.2%)で、次いで家族・親族(46.4%)となっています。
ケアマネジャーは、介護保険サービスの利用や介護計画の作成など、専門的な支援を行ってくれる心強い存在です。
私もそうでした。ケアマネの言葉に救われた話はこちらで紹介しています。
愚痴を言える相手がいない現実
介護のことで心配事や愚痴を聞いてもらうサポートを得られていたかについて、「そもそもサポートを受けられていない」と回答した人は46.6%にのぼります。
介護者が孤立しないためには、日常的に話を聞いてくれる存在が必要です。
愚痴を聞いてもらうだけでも精神的にはだいぶ楽になります。しかし、現状は約半数が愚痴も言えない状況ということです。これはかなり危険な状態で、いつか抱えきれなくなり、爆発してしまう可能性があります。
まとめ
介護が始まったとき、誰に相談するかは非常に重要です。職場や行政、ケアマネジャー、家族など、信頼できる相談先を見つけておくことが、介護生活を乗り越える鍵となります。
介護の悩みを一人で抱える必要はありません。相談することは、弱さではなく、介護を続けていくための強さです。
相談できる相手を持つことで、介護生活はぐっと楽になります。無理をしすぎず、自分自身のケアも忘れないでください。

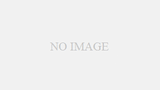
コメント