「親の介護なんて、まだまだ先の話」──そんなふうに思ってはいませんか?
実は、介護は思っているよりもずっと早く始まることが多いのです。40代・50代のうちに介護が始まり、突然日常が大きく変わってしまう人は少なくありません。ある日突然、子どもから“介護者”になる。そんな可能性は、誰にでもあるのです。
今回は、介護を始める年齢やきっかけとなる出来事に関する調査(三菱UFJリサーチ&コンサルティング「介護離職者の離職理由の詳細等の調査」)をもとに、私自身の経験も交えながら、介護のリアルをお伝えします。
介護の始まりは40代・50代が中心
厚生労働省の調査によると、介護を始めたときの介護者(世話をする側)の年齢は以下の通りです。
- 50代:35.6%
- 40代:24.7%
つまり、介護をしている人の約6割が40代~50代。
意外と早いと感じた方も多いのではないでしょうか。
私自身も、まさか40代で母の介護が始まるとは思っていませんでした。
母の言動に「あれ?」と思った違和感はありましたが、それが本格的な介護生活の始まりになるとは、その時は想像していなかったのです。
介護対象は「親世代」が大多数
被介護者、つまり介護を受ける側の年齢を見ると、以下のような結果が出ています。
- 80代:44.5%
- 70代:25.4%
これを見ると、介護対象はやはり親世代が中心であることが分かります。
人生の後半に差し掛かり、体力や認知機能が低下してくるタイミングで介護が必要になることが多いようです。
私の母も当時70代。年齢なりの衰えは感じていましたが、まさか本当に“介護”が必要なレベルになるとは……と、やはり現実を受け入れるまでには時間がかかりました。
介護のきっかけで最も多いのは「入院」や「認知症」
では、介護は何がきっかけで始まるのでしょうか?
主なきっかけは以下の通りです。
- 入院:37.9%
- 認知症の発症・進行:27.0%
つまり、入院や認知症をきっかけに介護が始まる人が非常に多いということです。
私も、母のおかしな言動がきっかけで病院を受診しました。診断は「アルツハイマー型認知症」。そこから母一人で暮らしていくのは難しく、介護が必要となりました。
このように、介護はある日突然やってくることがほとんどです。
備えがないまま介護が始まる現実
介護が始まる年齢も、きっかけも、ある程度データで予測できます。
しかし、それでも多くの人は「自分に限って、まだ先の話」と思ってしまうのが現実です。
私も、資産形成を通じて「もし親に何かあったら」とお金の準備だけはしていましたが、実際に介護が必要になったときは、生活の面でも精神面でも、準備不足を痛感しました。
仕事、家事、親のサポート……すべてを一人でこなす日々は、想像以上に大変です。
特に40代・50代は、働き盛りで仕事の責任も重く、子育てと介護の「ダブルケア」に直面する人も多い時期。介護が始まることで、仕事や生活に大きな影響が出てしまうケースも珍しくありません。
まとめ:介護は“明日”始まるかもしれない
介護は、ある日突然始まります。
「まさか、今自分が…」という気持ちのまま、生活が一変してしまうこともあります。
だからこそ、心の準備・情報の収集・経済的な備えが必要です。
介護に関する制度やサービスを知っておくだけでも、いざという時の負担はかなり違います。「まだ早い」と思っている今こそ、備えるタイミングです。
親の年齢や健康状態を一度見直し、もしもの時にどんな対応ができるのか、少しずつ考えてみませんか?

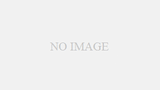
コメント